匍匐前進する三色猫だんご。

それはともかく、花見シーズン到来です。
花見といえばお団子なのですが、
雛祭りのときにもお店で同じものを見かけました。
三色団子(°_°
まあ、オールシーズン置いてあるんですけど。
*コンビニで見かけた『春の三色和菓子』


この色の組み合わせは、ど定番なのですね。
配置にきまりはあるのでしょうか。
ネット検索しますと、どっさり出てきます。
まず、よく見る解釈をご紹介。
▇ 色の配置
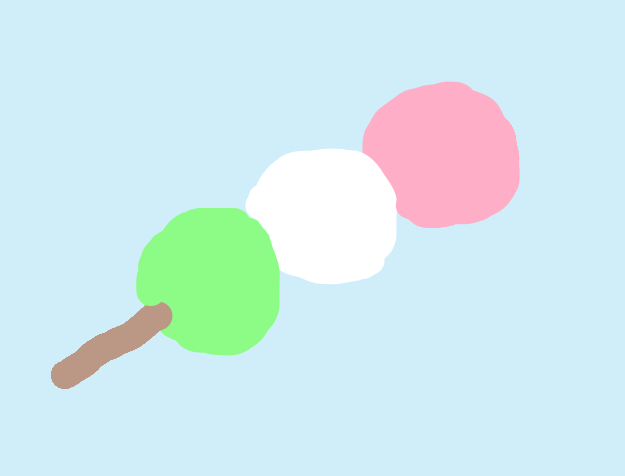
持ち手の方から、
緑 ➽ 白 ➽ ピンク(=赤)。
と、なっております。
▇ 色の意味:諸説あり
1.冬から春への移り変わりを表す。
*白:雪の色
*緑:新芽の色
*赤:花の色(または太陽の色)
白い雪の下で春の訪れを待つ植物の芽。
春の暖かな日差しに雪が解け、花が咲く。
2.桜の色の移り変わりを表す。
*赤:つぼみ
*白:花
*緑:葉っぱ
蕾が膨らみ、濃いピンク色に染まる。
満開の花は白く、散ると緑の葉が茂る。
3.日本の四季を表す。
*赤:春(花の色)
*白:冬(雪の色)
*緑:夏(新緑の色)
秋がない:秋無い=飽きない
秋無い→あきない→商い。
4.邪気払いの色。
*赤白:=(紅白)魔除け・邪気払い
*緑:邪気を祓うよもぎを表す。
赤には魔除けの効果あり(赤い褌など)。
紅白はめでたい配色でもあります。
5.ひな祭りの菱餅が由来。
*赤:桃の花
*白:白酒
*緑:よもぎ
重ねる順番は下から『緑 → 白 → 赤』。
土台が緑になるところが同じです。
^ー_ー^ どーでもよくなってきました。

私も疲れてきました。
では、こちらをごらんください。
▇ 花見団子・その2
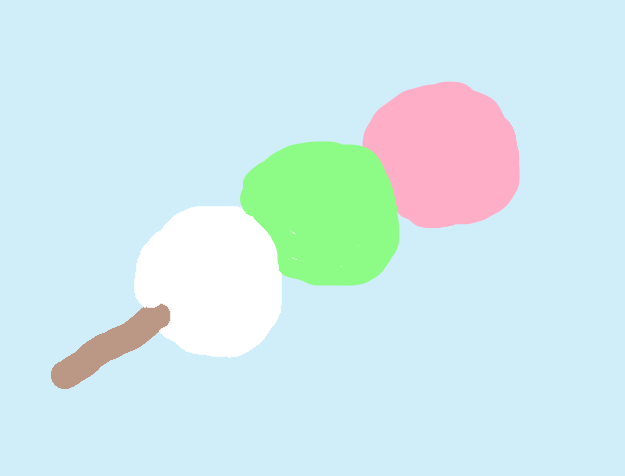
いかがですか。
さっきの絵と同じじゃないですよ。
なんだか違和感がありませんか?
あらためて、並べてみましょう。
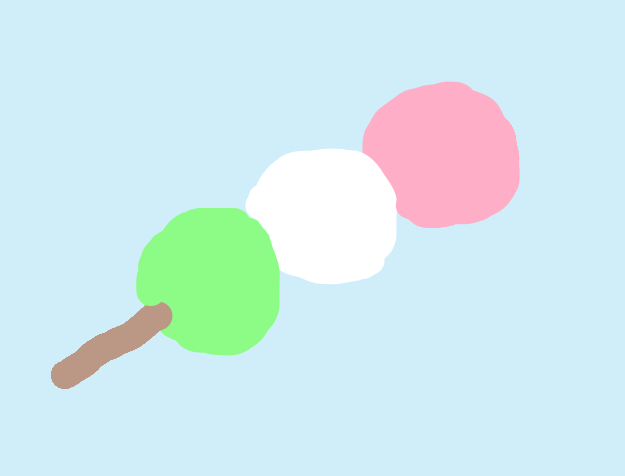
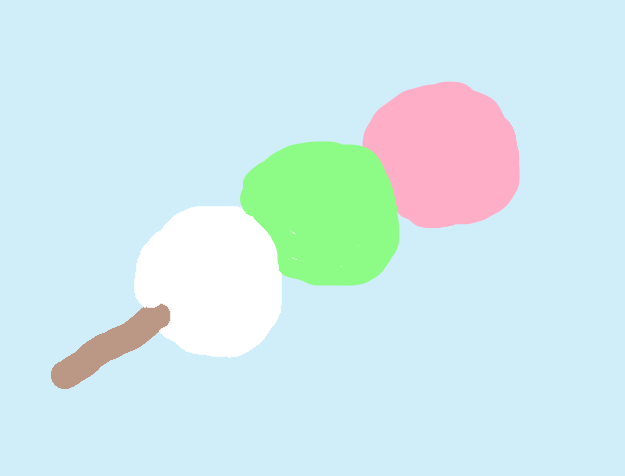
並び方が違いますね。
*左:よくある三色の花見団子。
桔梗屋さん。ピンとこなくても絶対ご存じですよ。
信玄餅のお店です(°▽°
▇ 花見団子いろいろ
花見団子は一種類じゃなかった。
*『秋』を表す色を入れた四色団子。
*『赤・白・緑』じゃない三色団子。
*串団子を羊羹でコーティングする。
*串に刺さない。
*団子がひらべったい。
…などなど。
地域差あり。
お店の中でもバリエーションあり。
個性豊かです。
ルールなんてどうでもいい。
『美味しい』は『正義』です。
▇ 菱餅の配色
花見団子が雛祭りの菱餅に由来するという説。
さっき、私は土台が『緑』と言いましたね。
あれも例外あり(°_°
雛飾りを見てみましょう。
写真素材がないので商品リンクです。
ご容赦ください。
*ひな人形七段飾り。
*ひな人形三段飾り。
はっはっは(°▽°
七段飾りの配色は、白が土台。
桔梗屋さんのお団子と同じです。
七段飾りの菱餅はもともと五重らしいですよ。
色も順番もさまざまだとか。
▇ 花見団子と秀吉?
花見団子を始めたのは、豊臣秀吉だという説。
これが、どうにも怪しいのです。
ネットの噂 → TV放映 → 定説化
なんだかこんな気配が漂ってきます。
※参照:お花見団子の始まりは秀吉??? | 一般社団法人 日本和食卓文化協会
秀吉と桜といえば、有名なのが
醍醐の花見。
桜を見ながら、ごちそうを食べる。
そういう大々的な宴を催しました。
団子も出たんでしょうかね(°_°
「醍醐の花見」が人々に強烈なインパクトを与えた。
それは事実だと思います。
※参考:豊臣秀吉│日本の食文化と偉人たち|未来シナリオ会議|キリン
『花見=桜の下で宴会』のルーツは秀吉かもしれません。
けれど『花見団子』のルーツは秀吉じゃない気がします。
気がするだけで、責任は持てません。
花見が一般大衆に広まったのは、江戸時代。
お団子なら、庶民にも手が届きますね。
『花見のお供=団子』
このあたりがルーツのような気がします。
【左から】 焦げ・ゴマ・タレ・きなこ。

※2021年3月2日撮影
^・ω・^ ゆったり更新中。よろしくなの。